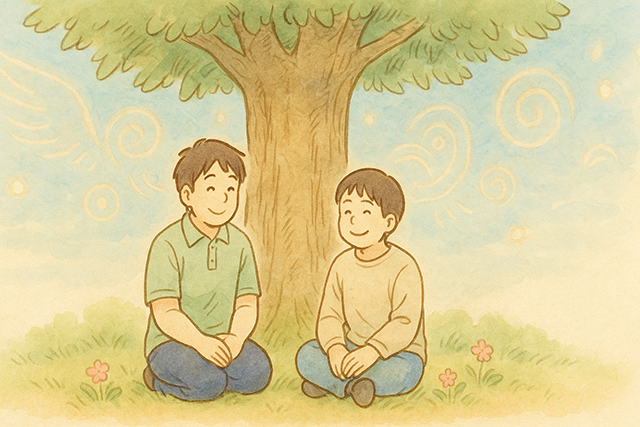こんにちは、鈴の音です。
10年後の福祉を考えるとき、私たちはただ未来を想像するだけではなく、そこに至るまでの道のりにも目を向ける必要があります。
支援の形は日々変わり続けますが、その根底にはいつも、誰かの声や行動がありました。
今の私たちの立っている場所も、決して突然現れたものではなく、積み重ねの上にあります。
今回は、「B型事業所のこれまでとこれから」について、見つめてみたいと思います。
◇拒まれた存在から、福をもたらす存在へ
障がいのある人の歴史は、制度の誕生よりもずっと前から、社会の中に存在していました。
日本最古の神話『古事記』には、イザナギとイザナミの間に生まれた“水蛭子(ヒルコ)”という子の記述があります。
体がうまく育たず、葦の舟に乗せられて海へ流されたこの存在は、「障がいがある」という理由で社会から排除された最初の記録のひとつかもしれません。
しかし、このヒルコは、やがて民間伝承のなかで海からやってきた“恵比寿様”として語られるようになり、福の神として人々に迎え入れられます。
拒まれた存在が、福をもたらす神として敬われるようになる――その流れは、排除された存在がやがて受け入れられ、敬意をもって迎えられるという象徴として、今の私たちの社会にも通じるものがあります。
また、江戸~明治にかけて各地に伝わる“福子伝説”も見逃せません。障がいのある子が生まれた家が繁栄する例が多かったことから、「福を呼ぶ存在」として大切にされるようになったという言い伝えです。
障がいのある子を守るために家族が団結し、力を合わせて暮らしていくなかで、自然と家運が高まっていった――そんな暮らしぶりに、希望や祈りを込めて伝えられてきたのかもしれません。「障がいのある子は家の宝」といった言葉も、そうしたまなざしを物語っています。
やがて時代が下るにつれて、障がいのある人々の居場所は家のなかから施設へ、そして地域へと少しずつ開かれていきました。
戦後の入所施設を経て、1980年代には地域の中で親や支援者が始めた小規模作業所が全国に広がり、2006年の制度改正によって、現在のB型事業所が誕生します。今ある制度は、こうした人々の思いや行動の積み重ねの上に成り立っています。
私たちは今、“巨人の肩の上”に立っているのかもしれません。
◇受け継がれてきた願いが、今のB型を支えている
「巨人の肩の上に立つ」とは、先人たちの努力の積み重ねによって、より遠くの未来を見渡せることを意味します。
私たちが今見ているB型事業所の風景も、先人たちの長年の歩みがあってこそのものです。
B型事業所に関する制度は、年月をかけて少しずつ整ってきました。その整備の背景には、「働くことを通じて、障がいのある方が地域の中でいきいきと暮らしていけるように」という願いがあります。
つまり、制度の目的は単なる作業の場を提供するだけにとどまらず、障がいのある方の人生そのものを支えることにあります。
こうした考えをもとに、ICT(情報通信技術)を活用した作業や地域の人たちとの交流、テレワーク的な取り組みなど、場所によってさまざまな工夫が広がっています。
作業内容も、モノづくりだけでなく、イベントや販売、創作活動など多彩になってきました。
今のB型事業所は、「ここで過ごすこと」自体に価値がある場として位置づけられています。
制度や支援といった枠組みを超えて、「ここに来る意味」をそれぞれが見いだせる――そんな新たな姿が広がりつつあります。
◇“人が人を大切にする”心が、福祉の未来をつくる
福祉の制度や仕組みは、人の思いによって形づくられてきました。これからも、障がいのある方々の存在を“ともにあるもの”として見つめ続けるかどうか――そのまなざしが、次の10年を変えていきます。
歴史を振り返ると、平和で豊かな時代には、障がいのある人々が地域のなかで大切にされていた例もあります。
一方で、戦乱や混迷の時代には、“弱さ”を抱える人が排除の対象となることもありました。
福祉は、時代の光と影を映す鏡のような存在でもあるのです。
これからの10年がどんな時代になるのか――それは誰にも分かりません。
でも、もしその未来が不安や分断に満ちたものであったとしても、“人が人を大切にする”というあたりまえの心が、福祉をかたちづくります。
◇鈴の音として、大切にしていきたいこと
鈴の音はこれからも、「この場所があったから、前を向けた」と感じてもらえるような存在でありたいと願っています。
作業や訓練の時間だけでなく、お茶を飲んで笑い合うひとときや、静かに過ごす時間も含めて、ここでの毎日が大切な時間となるように。
制度や形がどう変わっても、「ともに過ごす」という原点を忘れずに、鈴の音は、利用者さんといっしょに、これからの10年をつくっていきたいと思います。
鹿児島における就労継続支援b型事業所の全体像を確認したい方へ
この記事は就労継続支援b型事業所という大きなテーマの一部です。
関連する全ての記事の目次はこちらからご覧いただけます。
就労継続支援B型 in 鹿児島|あなたとご家族の「知りたい」を完全網羅した総まとめページ(目次)に戻る